DNAの電気抵抗を制御するメカニズムを発見
次世代のDNA半導体実現へ道を拓く
2004.08.13
独立行政法人物質・材料研究機構
NIMSの計算材料科学研究センターは、東北大学および独立行政法人産業技術総合研究所と共同で、DNAの電気伝導の理論と電気抵抗を制御する機構を見出した。
概要
- 独立行政法人物質・材料研究機構 (理事長 岸 輝雄) 計算材料科学研究センター (センター長 小野寺 秀博) の木野 日織 主任研究員と大野 隆央 副センター長は、東北大学 (総長 吉本 高志)の福山 秀敏 教授および 独立行政法人産業技術総合研究所 (理事長 吉川 弘之)の寺倉 清之 研究コーディネータのグループと共同で、DNAの電気伝導の理論と電気抵抗を制御する機構を見出した。
- 生体分子としてのDNAは、通常周りに金属イオンや水が存在している。本研究ではDNA分子のみならず、周りの金属イオンや水分子も含めたこれらの相互作用についてコンピュータシミュレーションによる電子状態の詳細な解析を行った。その結果、生体環境においては絶縁体であったDNAを、 (1) 特定の種類の金属イオンと結合し、さらに (2) その金属イオンの周囲の水分子を除去することにより半導体化することを見出した。
- これは、水分子を除去された金属イオンが結合しているDNA分子の内部に正孔を作るためである。そこに電圧を作用させると、定常的にできた正孔が電圧の向きに伝播することにより電流が生じ得る。また、この正孔の生じる程度 (密度) は金属イオンがどの程度存在するかによる。したがって、DNAの乾燥の程度などにより電気抵抗を制御することも可能であると考えられる。
- DNAの電気抵抗を測定する実験は世界中で行われているが、その結果に大きなばらつきが見られ、半導体および絶縁体の双方の結果が得られていたが、その原因は上に述べたようなメカニズムによるものと考えられる。
- 今後この理論に基づいたDNAの電気伝導性の制御技術開発が飛躍的に進展することが期待されるとともに、DNAの半導体細線としての利用、さらに自己組織化などのナノメートル (nm) サイズの特性を生かした、次世代の電子デバイスの開発が実現可能となる。本研究は、こうした革新的な分子デバイスの実現へ道を開くものである。
- 本研究成果は、JPSJ誌 (Journal of the Physical Society of Japan, 8月15日発行) に掲載される予定であり、同誌のLetters of editors' choiceに選定された。
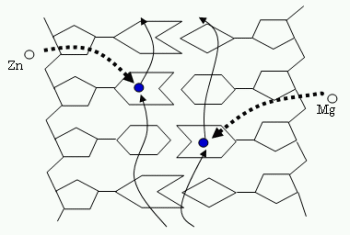
図1.周りに水のないマグネシウム (Mg) や亜鉛 (Zn) から正孔がDNAの塩基に移り、その正孔がDNAに電圧をかけるにより電気を運ぶ。金属イオンにあったときは自由に動けなかった正孔 (白丸) がDNAの塩基中では自由に動くことができる正孔 (青丸) になる。正孔が自由に動けるか動けないかは電子状態を調べることにより判定できる。
